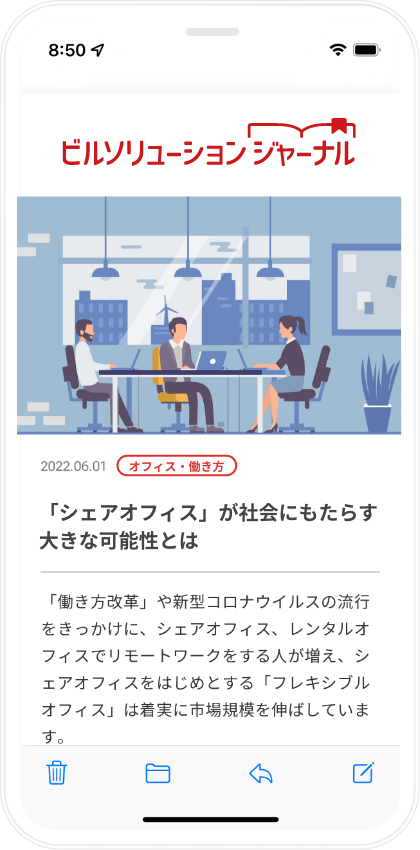デジタルサイネージは広告や販売促進の目的で使用され、街中の大型ビジョンから公共交通機関のディスプレイなど、さまざまな場所で見かけます。情報提供手段などとして市場規模は年々拡大しており、デジタルサイネージの目的も多様化しています。
デジタルサイネージを導入することで、どのようなメリットを得られるのでしょうか。また、どのような目的で導入されているのでしょうか。実例とともに解説します。
デジタルサイネージとは *1
デジタルサイネージとは屋外や店頭、公共交通機関などの場所でディスプレイ等の電子的な表示機器によって情報を発信するメディアです。普段の生活においては街頭の大型ビジョンやショッピングセンター、病院などで見かけられます。
デジタルサイネージは近年のディスプレイやネットワーク技術の発展によって、急速に市場が広まりました。電子看板という「屋外にある大型ビジョン広告」のイメージにとどまらないコンテンツ提供が可能です。
デジタルサイネージの市場規模
デジタルサイネージの市場規模は年々拡大を続けています。2025年の市場予測は3,186億円と2017年比の約2.2倍の成長です。

出所)一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム デジタルサイネージコンソーシアム取り組みのご紹介 p.10
https://www.soumu.go.jp/main_content/000649758.pdf業界別の市場規模を比べると、小売業界が最も大きな市場です。平均成長率は一般企業で高い伸びが見られます。

出所)一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム デジタルサイネージコンソーシアム取り組みのご紹介 p.12
https://www.soumu.go.jp/main_content/000649758.pdfすでに見られるデジタルサイネージの活用方法は以下のような事例です。*2
- ホテル・駅・空港などの案内ツール
- 金融機関における株価情報
- 小売店での値札
- 街の空間アート
- 公共空間での緊急情報
さまざまな広がりを見せているデジタルサイネージですが、今後は学校や病院の情報共有ツール、企業内の連絡ツールとしての活用も期待されています。*2
デジタルサイネージの種類 *3
デジタルサイネージは、主に2種類に分けることができ「スタンドアロン型」と「ネットワーク型」があります。
スタンドアロン型
スタンドアロン型は、ネットワークを必要としないタイプです。配信したいコンテンツをUSBメモリやSDカードに記録しておき、機器と直接つなぐことで情報を発信します。
スタンドアロン型のメリットは、インターネット環境がないところでもコンテンツ配信ができる点です。同じコンテンツを継続して配信する看板やポスターのようなイメージで使われます。
一方で、配信コンテンツを変更するときは、その機器がある場所まで行かなくてはならないデメリットもあります。
遠方に機器を設置している場合や、頻繁にコンテンツを変更する場合には適していません。近くに機器があり管理台数が少ないときや、一時的なイベントでコンテンツを変える必要がないときの利用に適しています。
ネットワーク型
ネットワーク型は、社内LANやクラウドなどのネットワークを通じてコンテンツ配信を行うタイプです。
遠方に設置されていたりコンテンツを頻繁に更新したりする場合に、遠隔で操作できる点がメリットです。複数拠点で緊急の情報を共有する手段としても利用できます。
しかしスタンドアロン型と比較した際に、配信管理システムに要するコストが高くなる点がデメリットといえます。
両方の特徴を理解し、実際の使用環境に合わせて選択しましょう。
デジタルサイネージの効果 *4
ここでは、デジタルサイネージを用いることで期待できる効果を3つに分けて見ていきましょう。
宣伝・販売促進
従来のチラシや看板では情報量に限りがありました。しかしアニメーションや音楽を用いることで、見た人の印象に残りやすく、宣伝・販売促進効果が期待できます。
コスト削減
ポスターやチラシを使用するときは、印刷するほどに紙やインク代が必要です。しかしデジタルサイネージでは、それら消耗品にかかる追加費用がかかりません。また、貼り替えに要する人的コストも抑えられます。
リアルタイムな情報提供
デジタルサイネージではタッチパネルやセンサー機能を活用することにより、利用者の必要な情報をリアルタイムで提供できます。また、タイマーやスケジュールを設定することで、柔軟な情報提供が可能です。
新たなデジタルサイネージの技術
では、このようなメリットを生かした使い方としてどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、デジタルサイネージの導入事例を2つ紹介します。
てらすガイド *5

出所)三菱電機ビルソリューションズ株式会社 てらすガイド
https://www.meltec.co.jp/building/guide/「てらすガイド」とは光のアニメーションを床面に映し出すことで、直感的で分かりやすい案内や注意喚起を行えるデジタルサイネージです。主な特徴を3つご紹介します。
- 多様な利用者に適したサインで業務効率化
光のアニメーションを使用することで高齢者・車いす利用者・外国人など、状況に適したサインを投影できます。標準実装以外にオリジナルのサインを作成できるので、用途に合ったサインを作成して、案内業務の効率化が可能です。 - 簡単に設置でき案内業務のコスト削減
事前の動画や画像の複雑な取り込みの必要もなく、コンセントさえあれば簡単に設置できます。イベントや時間に合わせた移動もできるので、貼り替え作業などのコスト削減が実現可能です。 - 他の設備と連携できる
設定したスケジュールや、他の設備と連動した表示ができるため、効率的な運用ができます。
こちらは実際に地下駐車場で「てらすガイド」を導入している事例です。
一般の駐車スペースと企業の駐車スペースが分かれているため、それぞれの進路を案内することで、スムーズな駐車を実現しています。

出所)三菱電機ビルソリューションズ株式会社 てらすガイド
https://www.meltec.co.jp/building/guide/また、混雑する時間帯では柔軟にサインを切り替えて、空いている駐車スペースの案内も行っています。

出所)三菱電機ビルソリューションズ株式会社 てらすガイド
https://www.meltec.co.jp/building/guide/あきどこサイネージ *6

出所)三菱電機システムサービス株式会社 あきどこサイネージ
https://www.melsc.co.jp/business/visual_solution/system/akidoko/「あきどこサイネージ」は、トイレの利用状況をリアルタイムで表示するデジタルサイネージです。利用状況だけでなく、混雑しているときは他フロアへの誘導、空いているときは広告の表示といったように、必要な情報提供を行います。
たとえば、商業施設において、あきどこサイネージを導入することで得られるメリットは次の3つです。
- 並ばなくて済むためお客様の満足度向上につながる
- お客様の時間が効率的に使えるため、購買時間と意欲の向上が見込める
- 利用状況が「見える化」できる
3の見える化については、長時間利用によるアラームを設定することでセキュリティ面での効果が期待できます。
あきどこサイネージはトイレだけでなく、レストランの利用状況やアトラクションの待ち時間、空港の荷物検査場の混雑具合を表示する際にも利用できます。
デジタルサイネージは情報発信と業務改善を両立できるシステム
今回はデジタルサイネージの効果や、新しい技術の導入事例などを解説しました。
ネットワーク技術の発展により、デジタルサイネージはさまざまな可能性を秘めています。企業側も今までの広告宣伝以外にも魅力を感じ、市場は拡大を続けています。
デジタルサイネージは、もはや単なる企業の宣伝ツールではありません。紙媒体よりもコストを削減しつつ、見る人にとって必要な情報を提供するシステムです。用途が多様化しているデジタルサイネージをうまく活用して、導入する企業も利用する人も有益に使っていきましょう。
- MAIL MAGAZINE
-
ビルに関わるすべての方に!ちょっと役に立つ情報を配信中
メール登録
*1
一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム デジタルサイネージとは
https://digital-signage.jp/about/
*2
一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム 広告メディアに留まらない可能性
https://digital-signage.jp/about/
*3
中小機構 ITプラットフォーム デジタルサイネージの種類・特徴
https://ittools.smrj.go.jp/info/feature/svdhaj00000002t7.php
*4
中小機構 ITプラットフォーム デジタルサイネージの効果
https://ittools.smrj.go.jp/info/feature/svdhaj00000002t7.php
*5
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 てらすガイド
https://www.meltec.co.jp/building/guide/
*6
三菱電機システムサービス株式会社 あきどこサイネージ
https://www.melsc.co.jp/business/visual_solution/system/akidoko/